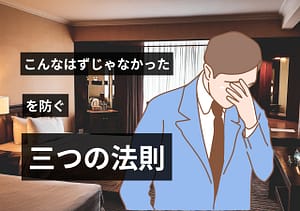開業直前に高い壁が・・・
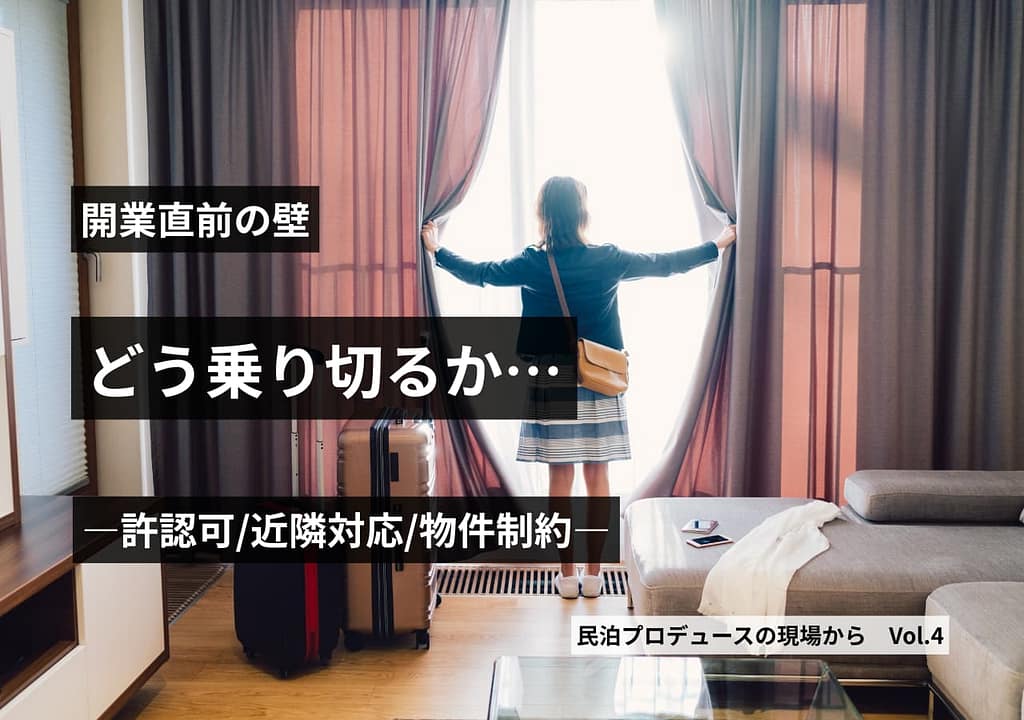
皆さんこんにちは!民泊.hub in 九州のカズマです。
私はこれまで【民泊.hub in 九州】のnote担当でした。今回からMAHOさんとともにブログもやっていきます!よろしくお願いします。
さて、民泊の現場で最も緊張感が走るのは、デザインでも集客でもなく「開業直前」のタイミングです。
開業準備といっても、物件自体の改修や家具の搬入だけでなく、営業に向けた許認可作業というものが発生します。
そのなかでも、私たち民泊.hubがプロデュースに関わる中で、一番多い相談が――
「旅館業法で行くべきか、住宅宿泊事業で申請すべきか分からない」という声です。
どちらも“民泊を運営できる許可”ですが、手続きもコストも、運営ルールもまったく違います。
そしてこの判断を誤ると、開業スケジュールも収益計画も一気に崩れます。
1. 「旅館業法」は365日営業できるけど、設備とコストが重い
旅館業法(簡易宿所)の最大の魅力は、365日営業できること。
年間を通じて宿泊を受け入れられるため、ハイシーズンの稼働を逃さず売上を伸ばせます。
ただし、実務ではここに大きな壁が立ちはだかります。
まず、消防・建築の基準が非常に厳しい。
避難経路の幅、感知器の設置位置、消火器の台数、非常照明の数まで細かく規定されています。
私たちも行政書士の先生と一緒に現地を回りながら、
「このドアは内開きではダメ」「廊下の幅が90センチ必要」など、現場で何度も修正を重ねました。
一度消防から“やり直し”が出ると、改修費用だけで数十万円単位の追加。
建物の構造によっては、そもそも旅館業での許可が取れないケースもあります。
つまり、旅館業法で進めるには「建築的に条件を満たす物件」+「設備投資を惜しまない覚悟」が必要です。

2. 「住宅宿泊事業法」はコストを抑えて始められる
一方、私たちが最近多く採用しているのが「住宅宿泊事業法(民泊新法)」です。
こちらは年間180日までの営業制限がありますが、
設備基準が緩やかで、既存住宅をそのまま活用しやすいというメリットがあります。
たとえば、避難経路やトイレの数に関しても柔軟性が高く、
消防設備も「住宅用火災警報器」で認められるケースが多い。
行政書士と現場を確認しながら、最小限の投資で合法的に運営できるのが最大の強みです。
もちろん、営業日数の制限があるため「フル稼働で利益を出したい」オーナーには物足りなく感じるかもしれません。
しかし実際には、繁忙期に集中的に予約を取り、閑散期をメンテナンス期間に充てることで、
180日でも十分な収益を確保できるケースが多いのです。
コストを抑えてリスクを最小化しながら始める――
これが、いまの民泊市場では最も現実的なスタートラインです。
3. 許認可よりも大事な「地域との関係」
どちらの申請方法を選んでも、最後に残る壁が「地域との関係」です。
開業の届け出が終わっても、実際に動き始めると近隣からの不安の声が上がることがあります。
私たちは行政書士と並行して、管理人・自治会・隣家への説明もセットで行います。
「旅行者が宿泊する施設になります」「夜間は静かに過ごしてもらいます」と誠実に伝えるだけで、
多くの方が理解を示してくれます。
地域と協力関係を築くことは、トラブル防止だけでなく、口コミ評価にも直結します。
“信頼される宿”は、リピーターを自然に増やしていきます。

4. 結論:コスパ重視なら「住宅宿泊事業」で始めよう
旅館業法は確かに理想的な形です。
でも、設備投資・時間・リスクを考えれば、
**現実的でコスパが良いのは「住宅宿泊事業」**です。
とくに初めて民泊を始めるオーナーや、副業・相続物件を活用したい方にとっては、
住宅宿泊事業からスタートし、運営を安定させてから旅館業へステップアップするのが王道ルートです。
民泊.hubでは、行政書士とタッグを組み、物件に合わせた最適な許認可ルートを一緒に考えます。
「法的に安全で、コスパの良いスタートを切る」――
それが、私たちが現場で実践してきた“リアルな答え”です。
✨ 次回予告
次回(第5回)は、「予約が入らない民泊の共通点と“埋まる宿”の違い」。
許認可を通した後の“運営の壁”を、データと現場の視点から深掘りします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2026年2月3日民泊オーナー診断その⑨|レビューが荒れる民泊の共通点
お知らせ2026年2月3日民泊オーナー診断その⑨|レビューが荒れる民泊の共通点 お知らせ2026年1月31日民泊オーナー診断その⑧|清掃で決まる:良い清掃パートナーの見抜き方
お知らせ2026年1月31日民泊オーナー診断その⑧|清掃で決まる:良い清掃パートナーの見抜き方 お知らせ2026年1月27日民泊オーナー診断その⑦|“丸投げ希望”でも成功する人/失敗する人
お知らせ2026年1月27日民泊オーナー診断その⑦|“丸投げ希望”でも成功する人/失敗する人 お知らせ2026年1月24日民泊オーナー診断その⑥|揉めるオーナー、揉めないオーナー
お知らせ2026年1月24日民泊オーナー診断その⑥|揉めるオーナー、揉めないオーナー